横山幸雄 ピアノ・リサイタル・シリーズ Voyage 第10回
第10回 モーリス・ラヴェル生誕140年記念 “音の魔術師”がピアノで描いためくるめく世界

©ミューズエンターテインメント
本公演は終了しました
2015年 8月2日(日) 15:00開演
| 【全席指定】 | 会員3,600円 一般4,000円 *U-23(23歳以下)2,000円 |
| * | U-23利用の中学生以上の方は、公演当日に身分証明書をご持参ください。 |
| 500円、対象:1歳~未就学児、定員10名、要予約(2週間前まで) *未就学児は入場できません。 |
|
| 【出 演】 | 横山幸雄 |
| 【曲 目】 | ラヴェル: 亡き王女のためのパヴァーヌ、ソナティナ、古風なメヌエット、水の戯れ、 鏡、高雅で感傷的なワルツ、ハイドンの名によるメヌエット、夜のガスパール |
Voyage第10回は、今年生誕140年を迎えるラヴェルの作品に焦点を当てます。
ピアノ曲をはじめ、あらゆるジャンルの作品を残した近代フランスを代表する作曲家のラヴェルは、第8回と第9回にご紹介したガブリエル・フォーレより作曲を学びました。
「亡き王女のためのパヴァーヌ」は、パリ音楽院在学中に作曲された彼の代表作の一つで、後に管弦楽版も作られました。フランツ・リスト作曲のピアノ曲「エステ荘の噴水」の影響を受けて作曲された「水の戯れ」は、水の流れや動きなどのあらゆる表情を描いた作品で、師であるフォーレに捧げられています。「鏡」はラヴェルの母の祖国スペインの特徴的なリズムを多用した組曲で、技巧的な名人芸が聴き所です。「夜のガスパール」は散文詩の先駆者として知られるフランスの詩人ベルトランの詩に基づいて作曲された作品で、オーケストラの響きを彷彿とさせる豊かな音色を味わうことができます。
ロマン派の流れを受け継ぎながら、フランス近代の新たな金字塔を打ち立てた音の魔術師、ラヴェルの色彩感あふれる作品の数々に存分に浸る贅沢なひとときに、どうぞご期待ください。
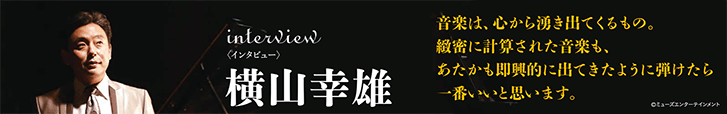
──横山さんは三鷹市ご出身ということで、今までも何回も当財団の事業にご出演をいただいております。
ええ。生まれた頃から三鷹駅の南口付近に住んでいて、市内の明泉幼稚園卒園で、市立第三小学校に3年生の途中まで通っていました。
──1987年、16歳でパリの国立高等音楽院に留学されましたが、その当時の思い出は?
 留学した年がちょうどラヴェルの没後50年だったんです。50年前というと自分たちの祖父母かその上の時代というくらいで、ショパンやベートーヴェンに比べると割と身近に感じられますよね。ラヴェルは写真も残っているし、パリの街の風景も当時とあまり変わっていないだろうし。その年の夏にラヴェルの生まれたフランス南西部のバスク地方で、音楽のサマーセミナーのようなものがあり、記念イヤーなのでオーケストラと一緒にラヴェルのピアノ協奏曲を弾けるという企画があったんです。ラヴェルには、両手の作品と左手だけのための作品の2つの協奏曲があるのですが、左手の協奏曲を弾く人が誰もいないというので、僕も当時は弾いたことがなかったのですが、「やってみようか」と思い急きょ譜読みをして演奏したという思い出があります。結果がどうだったのかはよく覚えていないのですが…まさか弾けると思わなかったのですが、大きなミスはなく出来たんじゃなかったかなぁ(笑)。
留学した年がちょうどラヴェルの没後50年だったんです。50年前というと自分たちの祖父母かその上の時代というくらいで、ショパンやベートーヴェンに比べると割と身近に感じられますよね。ラヴェルは写真も残っているし、パリの街の風景も当時とあまり変わっていないだろうし。その年の夏にラヴェルの生まれたフランス南西部のバスク地方で、音楽のサマーセミナーのようなものがあり、記念イヤーなのでオーケストラと一緒にラヴェルのピアノ協奏曲を弾けるという企画があったんです。ラヴェルには、両手の作品と左手だけのための作品の2つの協奏曲があるのですが、左手の協奏曲を弾く人が誰もいないというので、僕も当時は弾いたことがなかったのですが、「やってみようか」と思い急きょ譜読みをして演奏したという思い出があります。結果がどうだったのかはよく覚えていないのですが…まさか弾けると思わなかったのですが、大きなミスはなく出来たんじゃなかったかなぁ(笑)。
──ラヴェル自身に全曲指導を受けた先生からレッスンを受けたそうですね。
ヴラド・ペルルミュテール先生という方で、僕のパリ音楽院時代の先生(ジャック・ルヴィエ)の先生だった方ですが、当時すでに高齢でリタイアされていましたが、何回か個人的にレッスンを受ける機会がありました。一言一言に重みがあって、若い僕には知り得ないような人生の歴史を感じましたね。
──「音の魔術師」と言われるラヴェルですが、横山さんはラヴェルの音楽をどのように感じていらっしゃいますか?
 ラヴェルの場合、まず、音の選び方が特に厳選されているんですね。音楽は通常、バッハ、ベートーヴェン、ショパン…と時代を経る流れの中でやや複雑な方向に向かって行くんですが、ラヴェルは聴いていて理解が出来る最高限度の複雑さ、と言ったらいいのでしょうか、これ以上複雑だと混沌になってしまうというギリギリの所の研ぎ澄まされた感性と、非常に抑制されたロマンティシズムというのがあると思います。
ラヴェルの場合、まず、音の選び方が特に厳選されているんですね。音楽は通常、バッハ、ベートーヴェン、ショパン…と時代を経る流れの中でやや複雑な方向に向かって行くんですが、ラヴェルは聴いていて理解が出来る最高限度の複雑さ、と言ったらいいのでしょうか、これ以上複雑だと混沌になってしまうというギリギリの所の研ぎ澄まされた感性と、非常に抑制されたロマンティシズムというのがあると思います。
非常に緻密に計算された音楽なんですけど、その構造が全く見えないというのも意味をなさないけれど、それが計算されたものとして聞こえてしまってはちょっと違うと思うんです。弾く側としては、それを自然な流れのように感じさせられれば、それが理想の演奏ではないかと思います。例えば料理を食べた時、すぐレシピがわかっちゃうというのも最終的には感動できないんじゃないかと思うんですよね。なんだかわからないけどおいしいよね、というのが感動を呼ぶんじゃないかと…。この例えでいいのかな(笑)。
──今回のプログラムの構成はいかがですか?
今回は、ラヴェルが早い時期に書いた小品を中心にしています。「亡き王女のためのパヴァーヌ」や「水の戯れ」など、メロディが美しく、音大進学を目指している方や、少々本格的にピアノを学習している方たちによく演奏される曲もあります。一方、「夜のガスパール」はこの世で一番難しいと言われる曲で、この曲は、当時ロシアのバラキエフが作曲した「イスラメイ」という曲が演奏技術的に最も困難と言われていたんですが、それに匹敵するかそれを超えようとして書いたと言われています。ただ、聴き手にとって難解でわからない、という種類の曲ではないですよ。
──今回のコンサートでも横山さんのトークは入りますか?
今回と、次の回でラヴェルの作品を網羅する予定なんです。そうすると、作品の移り変わりがわかった方がより理解が深まるということもあると思うのでお話も加えた方がいいかもしれませんね。
──三鷹の風のホールは今年、20周年を迎えます。
 僕は折に触れて話しているのですが、三鷹のホールは響きがいいんです。そしてニューヨーク・スタインウェイのピアノが入っているのは珍しいので、僕は気に入って何度も弾かせてもらっています。20年経つということでちょうどホールもピアノも一番輝いている場所ではないかと思います。そういう楽器とホールで、ピアノという楽器の表現の可能性を感じさせてくれる作品の数々が演奏できるのは楽しみですね。
僕は折に触れて話しているのですが、三鷹のホールは響きがいいんです。そしてニューヨーク・スタインウェイのピアノが入っているのは珍しいので、僕は気に入って何度も弾かせてもらっています。20年経つということでちょうどホールもピアノも一番輝いている場所ではないかと思います。そういう楽器とホールで、ピアノという楽器の表現の可能性を感じさせてくれる作品の数々が演奏できるのは楽しみですね。
──演奏活動以外にも、大学では後進の育成、ラジオ番組への出演、レストランの経営もされワインエキスパートの資格も持つなど、マルチなご活躍をされている横山さんですが、今後の抱負はいかがでしょうか?
音楽に対しては計画を立ててやるんですが、その他のことについては、結構何にでも興味がある方なんで広いマインドは持っているようにして、人との出会いや交流を大切にしていった結果こうなったという感じなんです。まあ、僕の最終的な目標は自分の音楽のクオリティをどこまで上げられるかということですが、それは家に籠って勉強をするだけでないと思います。それは原点ですが、いろんなことを経験して音楽の幅が広がっていけばいいな、と考えています。
(2015年5月7日J:COM武蔵野三鷹にてインタビュー)
 留学した年がちょうどラヴェルの没後50年だったんです。50年前というと自分たちの祖父母かその上の時代というくらいで、ショパンやベートーヴェンに比べると割と身近に感じられますよね。ラヴェルは写真も残っているし、パリの街の風景も当時とあまり変わっていないだろうし。その年の夏にラヴェルの生まれたフランス南西部のバスク地方で、音楽のサマーセミナーのようなものがあり、記念イヤーなのでオーケストラと一緒にラヴェルのピアノ協奏曲を弾けるという企画があったんです。ラヴェルには、両手の作品と左手だけのための作品の2つの協奏曲があるのですが、左手の協奏曲を弾く人が誰もいないというので、僕も当時は弾いたことがなかったのですが、「やってみようか」と思い急きょ譜読みをして演奏したという思い出があります。結果がどうだったのかはよく覚えていないのですが…まさか弾けると思わなかったのですが、大きなミスはなく出来たんじゃなかったかなぁ(笑)。
留学した年がちょうどラヴェルの没後50年だったんです。50年前というと自分たちの祖父母かその上の時代というくらいで、ショパンやベートーヴェンに比べると割と身近に感じられますよね。ラヴェルは写真も残っているし、パリの街の風景も当時とあまり変わっていないだろうし。その年の夏にラヴェルの生まれたフランス南西部のバスク地方で、音楽のサマーセミナーのようなものがあり、記念イヤーなのでオーケストラと一緒にラヴェルのピアノ協奏曲を弾けるという企画があったんです。ラヴェルには、両手の作品と左手だけのための作品の2つの協奏曲があるのですが、左手の協奏曲を弾く人が誰もいないというので、僕も当時は弾いたことがなかったのですが、「やってみようか」と思い急きょ譜読みをして演奏したという思い出があります。結果がどうだったのかはよく覚えていないのですが…まさか弾けると思わなかったのですが、大きなミスはなく出来たんじゃなかったかなぁ(笑)。 ラヴェルの場合、まず、音の選び方が特に厳選されているんですね。音楽は通常、バッハ、ベートーヴェン、ショパン…と時代を経る流れの中でやや複雑な方向に向かって行くんですが、ラヴェルは聴いていて理解が出来る最高限度の複雑さ、と言ったらいいのでしょうか、これ以上複雑だと混沌になってしまうというギリギリの所の研ぎ澄まされた感性と、非常に抑制されたロマンティシズムというのがあると思います。
ラヴェルの場合、まず、音の選び方が特に厳選されているんですね。音楽は通常、バッハ、ベートーヴェン、ショパン…と時代を経る流れの中でやや複雑な方向に向かって行くんですが、ラヴェルは聴いていて理解が出来る最高限度の複雑さ、と言ったらいいのでしょうか、これ以上複雑だと混沌になってしまうというギリギリの所の研ぎ澄まされた感性と、非常に抑制されたロマンティシズムというのがあると思います。 僕は折に触れて話しているのですが、三鷹のホールは響きがいいんです。そしてニューヨーク・スタインウェイのピアノが入っているのは珍しいので、僕は気に入って何度も弾かせてもらっています。20年経つということでちょうどホールもピアノも一番輝いている場所ではないかと思います。そういう楽器とホールで、ピアノという楽器の表現の可能性を感じさせてくれる作品の数々が演奏できるのは楽しみですね。
僕は折に触れて話しているのですが、三鷹のホールは響きがいいんです。そしてニューヨーク・スタインウェイのピアノが入っているのは珍しいので、僕は気に入って何度も弾かせてもらっています。20年経つということでちょうどホールもピアノも一番輝いている場所ではないかと思います。そういう楽器とホールで、ピアノという楽器の表現の可能性を感じさせてくれる作品の数々が演奏できるのは楽しみですね。