バロック・オーボエの女王レフラーとAkamusで聴く、ヴェネツィアのきらめき
ベルリン古楽アカデミー
“協奏曲とシンフォニア”─ヴェネツィアの風に吹かれて

クセニア・レフラー
(バロック・オーボエ独奏)
©Daniel Maria Deute

ゲオルク・カルヴァイト
(ヴァイオリン独奏、コンサートマスター)
©Kristof Fischer
本公演は終了しました
2016年 6月26日(日) 15:00開演
| 【全席指定】 | 会員 S席5,400円・A席4,500円 一般 S席6,000円・A席5,000円 *U-23(A席/23歳以下)3,000円 |
| * | 中学生以上の方は公演当日に学生証または年齢が確認できるものをご持参ください。 |
| 500円、対象:1歳~未就学児、定員10名、要予約(2週間前まで) *未就学児は入場できません。 |
|
| 【出 演】 | ベルリン古楽アカデミー(略称アカムスAkamus) クセニア・レフラー(バロック・オーボエ独奏) ゲオルク・カルヴァイト(ヴァイオリン独奏、コンサートマスター) |
| 【曲 目】 | ヴィヴァルディ:弦楽と通奏低音のための協奏曲ハ長調RV114、オーボエ協奏曲ハ長調RV450 カルダーラ:シンフォニア第12番『我らイエスの受難』 アルビノーニ:5声のソナタ イ長調op.2-3 ヴィヴァルディ: 2つのヴァイオリンのための協奏曲イ短調RV522(『調和の霊感』より第8番) テッサリーニ:『ラ・ストラヴァガンツァ(風変わり)』op.4より序曲ニ長調 A.マルチェッロ:オーボエ協奏曲ニ短調 ヴィヴァルディ:ヴァイオリンとオーボエのための協奏曲変ロ長調RV Anh.18(RV364による) |
世界有数のバロック・オーケストラの一つと目されるベルリン古楽アカデミー(略称アカムスAkamus)が、1999年6月(共演:クリストフ・プレガルディエン/テノール)、2012年12月(ジャン=ギアン・ケラス/チェロ)に引き続き、風のホールに三度目の登場です。小編成の室内楽から大編成のオーケストラ作品、ルネ・ヤーコプス(指揮)とのオペラやオラトリオ作品の上演、コンテンポラリーダンスの第一人者サシャ・ヴァルツ&ゲスツとのコラボレーションなど幅広い演奏活動でも知られています。これまでに、100万枚を超えるレコーディング・セールスを記録し、グラミー賞、エコー賞、ディアパゾン・ドール賞、カンヌ・クラシック賞、グラモフォン賞、エディソン賞など国際的な賞を次々と受賞しています。
今回は2014年にリリースされたCD『ヴェネツィアの黄金時代』の収録曲をメインに据え、17世紀から18世紀にかけて文化の爛熟期にあったヴェネツィアで生まれたヴィヴァルディと彼の同時代の作曲家の音楽に迫ります。特に、このプログラムではオーボエ協奏曲がメインに据えられています。ヴィヴァルディはその生涯に約20曲ものオーボエ協奏曲を作曲しましたが、そのうち何曲かは彼が勤めていたピエタ慈善院付属音楽院のオーボエの名手、ペッレグリーナという女性が演奏したと言われています。
このほかにも、哀愁を帯びた緩徐楽章が70年代のイタリア映画『ヴェニスの愛』で使われたことで有名になったアレッサンドロ・マルチェッロのオーボエ協奏曲ニ短調も演奏されます。
オーボエ独奏は、2001年からベルリン古楽アカデミーのメンバーで首席オーボエ奏者を務め、“バロック・オーボエの女王”とも称されるクセニア・レフラーです。彼女の美しくメロウで温かな音色を、波打つラグーナ(潟)のように躍動感ある通奏低音と鮮やかな色彩に彩られたAkamusのヴィヴィッドなアンサンブルでじっくりとご堪能ください。

1982年に旧東ベルリンで設立されて以来、オペラやオラトリオ、コンテンポラリーダンスとのコラボレーション
公演など幅広い演奏活動で注目される世界有数のバロック室内オーケストラの一つ、ベルリン古楽アカデミー(略称Akamus)。Akamusは1999年、2012年に引き続き風のホールには3度目の登場となります。
『協奏曲とシンフォニア〜ヴェネツィアの風に吹かれて〜』の公演で約3年半ぶりの来日となるAkamusのコンサートマスターの一人、ゲオルク・カルヴァイトさんとソリストのオーボエ奏者、クセニア・レフラーさんにメールでインタビューにお答えいただきました。
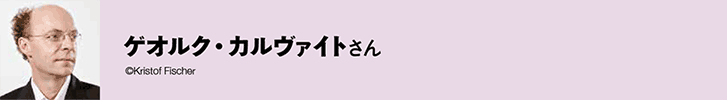
■ヴァイオリンとの出会い
子どもの頃から音楽は家庭でいつも重要な役割を果たしていましたね。父は医師であり、情熱的なヴァイオリン奏者でした。幼い頃、毎年5月に行われていた「グライフスヴァルト*・バッハ週間」という教会主催の音楽祭で、私はバッハの受難曲やその他有名なバロック音楽の作品に出会いました。その後ヴァイオリンを始め、バッハ・ギムナジウム(中等学校)を経て、ベルリンのハンス・アイスラー音楽大学に進学したのですが、旧東ドイツだったため、バロック・ヴァイオリンや古楽を勉強することはとても考えられませんでした。旺盛な好奇心と音楽そのものが私の先生だったのです。
*グライフスヴァルト:ドイツ北東部、バルト海沿岸のリック川河口に位置する旧東ドイツの小さな港湾都市
■ヴァイオリンとの出会い
バロック音楽を学んでいて、大学では答えを得ることもできない課題や悩みを抱えたのですが、私はそのような時、Akamusの知り合いの演奏家たちと連絡を取りました。その後、あるプロジェクトでより大きな弦楽セクションが必要となった際に、彼らからアンサンブルへの誘いを受けたのです。もちろん私は彼らと一緒に演奏をしたかったので、すぐにオーケストラのメンバーになりました。
■今回のプログラムについて
Akamusは長年にわたり、主にヨハン・セバスティアン・バッハ周辺のドイツの音楽に積極的に取り組んできました。ですから、イタリアの音楽との関わりは、私たちのツアーのいわば副産物のようなものだったんですね。1枚のCDをまるごとアントニオ・ヴィヴァルディの協奏曲に特化するというアイディアを自分たちのレーベルでもあるハルモニア・ムンディ・フランスと共に実現しました。この録音が批評家から絶賛されたことから、私たちはさらにイタリア音楽を探求しようという勇気を持つことができました。ジャン=ギアン・ケラスとのCD(ヴィヴァルディのチェロ協奏曲)は、この進化の過程で必然的に生まれたものです。そこで私たちは、ヴィヴァルディの時代のあまりよく知られていなくとも優れた音楽をさらに念入りに調べることにしました。その仕事を進めるなかで、ぜひとも日本の皆様にも紹介したいと思える、素晴らしい音楽を発見したのです。
■最後にメッセージをお願いします。
私たちAkamusは、この国の文化、コンサートホールの優れた音響ほか多くのことに高く敬意を表しています。今回のツアーでも、親切で熱心な日本の皆様にお目にかかりますことを、とても楽しみにしています。
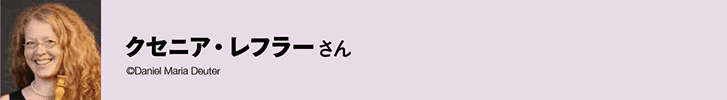
■初めに自己紹介をお願いします。
私は、ドイツのエアランゲンという街で育ちました。初めて演奏した楽器はリコーダーで、5歳の時に始めました。13歳でチェロも演奏するようになり、今でも自宅にいる時だけ弾いています。リコーダーとバロック・オーボエをスイスのバーゼル・スコラ・カントルムで学びました。リコーダーは今でも大好きですし、Akamusと一緒にリコーダーで演奏する機会も時々あります。現在はベルリン芸術大学とブレーメン芸術大学でも教えています。生徒9人のうち2人が日本人なんですよ!
■オーボエ、バロック・オーボエとの出会いについて
オーボエは人間のあらゆる感情を自然に表現できる楽器の一つだと思います。幅広い音域の中で音色や強弱を自在に変えられるのもオーボエならではです。
オーボエの音とバロック時代にオーボエのために書かれた美しい作品の数々に、私はいつも魅了されていました。バロック・オーボエの音を初めて聴いた瞬間、この楽器を勉強したい、という思いが鮮明になったのです。当時はリコーダーとチェロを演奏していたので、オーボエ奏者になることが目標ではありませんでしたが、この楽器の練習にのめり込むようになったのは言うまでもありません。
■マルチェッロ、ヴィヴァルディのオーボエ協奏曲について
今回取り上げる3つの協奏曲は、どれも私の大好きなものばかりです。マルチェッロの協奏曲は、最も有名なオーボエの作品の一つなので、ご存じの方も多いでしょう。ヨハン・セバスティアン・バッハは、この作品をチェンバロ用に編曲しました。ヴィヴァルディのオーボエ協奏曲は、色彩とユーモアに溢れた二つの急速楽章と、メランコリックで暗い色彩の緩徐楽章から成り立っています。オーボエとヴァイオリンのための協奏曲は、私たちがドレスデンの図書館で見つけた作品です。バッハの時代のドレスデンの宮廷楽団には優秀な音楽家たちが集まっていたので、欧州一のオーケストラとみなされていました。18世紀初期のヴェネツィアで、ヴィヴァルディと会った者もいます。ヴィヴァルディはドレスデンの才能豊かな名手たちを賞讃し、彼らのために素晴らしい音楽を作曲しました。この作品は、まさに、彼がドレスデンの友人たちのために特別に作曲した作品の一つだったのです。
■最後にメッセージをお願いします。
三鷹で皆様と一緒にヴェネツィアへの音楽の旅に出かけるのをとても楽しみにしています。皆様が目を閉じて、ヴェネツィアの有名な“ラグーナ”(潟)のイメージを思い浮かべられるような雰囲気を作ることができれば、とても嬉しく思います。終演後にはぜひお会いしましょう!
プログラムや楽器、音楽についてお尋ねになりたいことがありましたら、どうぞ、私に声をかけてくださいね!

