古楽のスペシャリスト達によるバロック時代の人々を魅了した活気あふれる劇音楽の魅力に迫る!

水内謙一(リコーダー)
パウル・エレラ(ヴァイオリン)

戸田 薫(ヴァイオリン)
天野寿彦(ヴィオラ)

エマニュエル・ジラール(チェロ)
村上暁美(チェンバロ)
(cc) Bas Lammers
本公演は終了しました
2014年12月6日(土) 17:00開演
| 【全席指定】 | 会員3,400円 一般3,800円 *U-23(23歳以下) 2,000円 |
| * | 中学生以上の方は公演当日に学生証または年齢が確認できるものをご持参ください。 |
| 500円、対象:1歳~未就学児、定員10名、要予約(2週間前まで) *未就学児は入場できません。 |
|
| 【出 演】 | 水内謙一(リコーダー) パウル・エレラ(ヴァイオリン) 戸田 薫(ヴァイオリン) 天野寿彦(ヴィオラ) エマニュエル・ジラール(チェロ) 村上暁美(チェンバロ) |
| 【曲 目】 | ダニエル・パーセル:<恋の仲直り>より組曲 エクルズ:<狂える恋人>よりエア集 ペプシュ(編曲):<乞食オペラ>よりグリーンスリーヴス、 スコットランド民謡、リリブレロ等 ほか |
17世紀から18世紀半ばのヨーロッパでは、イタリアで歌劇が誕生し、その後貴族や宮廷を中心にフランスでも興隆しました。一方、イギリスのロンドンでは16世紀のエリザベス朝時代に演劇文化が花開き、当時の世相に基づく風刺詩や曲のパロディに詞をつけた音楽劇が生まれました。人々は身分の違いは関係なく、劇場に集い、様々な演劇を楽しんだといわれています。当初、劇の脇役に過ぎなかった音楽は、バロック時代になると重要な役割を果たすようになり、幕間の余興では楽団のトップの奏者がソロやアンサンブルを披露して人々を沸かせました。宮廷音楽が栄えた一方で、ロンドンでは物語の特徴を精巧に表現した劇音楽が人気を博していたのです。
今日では演奏機会も減り、埋もれてしまっていた当時の劇音楽が、この度風のホールにリコーダーとヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、チェンバロという編成で甦ります! 17世紀における劇音楽の人気作曲家であったエクルズの「狂える恋人」や、イギリス音楽発展の立役者の一人であるダニエル・パーセルが作曲した「恋の仲直り」など、それぞれの場面の情景をイメージさせるわかりやすい旋律や、ウィットに富んだコミカルな作品が登場します。また、これらは演奏者自身が何度もロンドンの図書館に直接足を運んで発掘した貴重な作品です。
バロック時代では、音楽はキャンドルの灯りの中で演奏されていました。このコンサートではその様子を再現すべく、ステージを素敵なキャンドルで囲んでお贈りします。
ロマンティックな灯りの中で、当時の劇音楽を楽しんでみませんか?
【水内謙一さんインタビュー動画】
※J:COM武蔵野三鷹「MITAKA ARTS NEWS ON TV vol.133」で放映されたものです。YouTube で見る
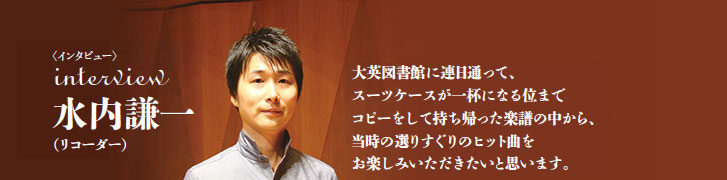
──水内さんのリコーダーとの出会いは小学校ですか?
 そうです。皆さんと同じように小学校の授業でやって、結構好きだったようで、学校の帰りに吹きながら帰ったりしていました。
そうです。皆さんと同じように小学校の授業でやって、結構好きだったようで、学校の帰りに吹きながら帰ったりしていました。
──東京藝術大学の楽理科へ進まれましたね。
楽理科は、音楽史や音楽の学問的な部分を扱う学科なのですが、頭でっかちになっちゃいかんな…と思いまして、僕はバロック音楽が大好きだったので、リコーダーをやり始めました。やり始めたらリコーダーの方にどんどんはまって行って今に至る、という感じです。(笑)
──その後ドイツのケルン音楽大学へ留学されましたが、いかがでしたか?
ドイツには5年半いましたが、風土や文化を肌で感じられたのが良かったです。日常生活でも、例えばスーパーでレジの人が、知り合いと出会って会話をし始めたら、お客さんも黙ってそれが終わるまで待っているとか(笑)、日本では考えられない時間の感覚があったりして、住んでみないとわからない色々な体験ができました。ドイツでは古楽を学んだのですが、リコーダーのソロの曲だけでなく、アンサンブルの中での魅力を強く感じるようになりました。オーケストラの中ではリコーダーは常に演奏している楽器ではないですが、リコーダーが出てきたときに甘い音色になったり、華やかさが増したり、リコーダーの音色の持つキャラクターに、より魅かれるようになりました。それが、帰国してからも、色々な曲を開拓しつつ弦楽器やチェンバロと一緒にリコーダーを魅力的に使うという活動につながっています。大変素朴な楽器ですが、例えばソプラノリコーダーは、弦楽器の方と一緒に吹くと大体1オクターブ上の音になるので、華やかな魅力が出るんですよ。
──楽譜については水内さんご自身で発掘もされたそうですね。
そうなんです。今回の楽譜は共演のチェンバロの村上さんと大英図書館に連日通って、セルフコピー可能な昔の楽譜を、小型のスーツケースが一杯になるくらいまで必死にコピーをして持ち帰りました。帰国して片っ端から音を出して、じっくり向き合ってみると思いがけない所から「この曲は面白い」とか「いい曲だな」というのが出てくることがあり、今回のコンサートはそうやって見つけた曲やヒット曲の中からオムニバス方式でお楽しみいただくことになります。
──当時のロンドンの劇音楽とはどのようなものだったのでしょうか?
 ロンドンの劇音楽と言うとシェイクスピアが有名ですが、シェイクスピアの時代には劇に音楽が挿入されていて、シェイクスピアの死後もロンドンではシェイクスピアや新たな名作の上演が盛んでした。時を経て段々音楽の要素が大きくなってきて、劇場には楽団も出来てミュージカルさながらに、音楽とお芝居の両方が楽しめる一大エンターテイメントになっていきました。17世紀の末には劇場に足を運ぶことは最大の楽しみだったと言われています。まさにそういう場所で演奏された曲を今回演奏することになります。
ロンドンの劇音楽と言うとシェイクスピアが有名ですが、シェイクスピアの時代には劇に音楽が挿入されていて、シェイクスピアの死後もロンドンではシェイクスピアや新たな名作の上演が盛んでした。時を経て段々音楽の要素が大きくなってきて、劇場には楽団も出来てミュージカルさながらに、音楽とお芝居の両方が楽しめる一大エンターテイメントになっていきました。17世紀の末には劇場に足を運ぶことは最大の楽しみだったと言われています。まさにそういう場所で演奏された曲を今回演奏することになります。
劇中で演奏されていた音楽から抜粋して当時10年間くらい定期刊行されていた器楽曲集があるのですが、その中から発見した曲も演奏します。人々が華やかに踊っていたり、主人公が悲しんでいたり、情景が思い浮かぶようなわかりやすい曲が多く、舞台上のめくるめく世界の様々な要素が出てくるので、それが楽しいと思います。
──今回は6名の編成ですね。
はい。今申し上げた劇音楽の器楽曲集は4声部で出来ているんですが、それを6人で演奏するのでヴァイオリンパートにリコーダーが1オクターブ上で入るとか、弦だけで演奏するとか、音を出してみながら編成を決めていきます。当時の人もアイデアで楽器を加えていたと思いますが、今回は私達が、その曲のキャラクターを表すのに良いと思う編成を選んでやっていきたいと思います。
──具体的な曲目を少しご紹介いただけますか?
 まず、「乞食オペラ」はジョン・ゲイが書いた1700年代にロンドンで大ヒットした音楽劇で、乞食や泥棒が登場する社会風刺作品です。この作品では音楽がオリジナルではなく、当時誰もが知っている民謡などのポピュラーソングに、台本に合った歌詞を当てはめるという替え歌のようになっているところが特徴で、例えばグリーンスリーヴスのような曲が入っています。当時の人がどんな音楽を楽しんでいたかがわかりますし、中でも面白い曲をつなげてお贈りしたいと思います。
まず、「乞食オペラ」はジョン・ゲイが書いた1700年代にロンドンで大ヒットした音楽劇で、乞食や泥棒が登場する社会風刺作品です。この作品では音楽がオリジナルではなく、当時誰もが知っている民謡などのポピュラーソングに、台本に合った歌詞を当てはめるという替え歌のようになっているところが特徴で、例えばグリーンスリーヴスのような曲が入っています。当時の人がどんな音楽を楽しんでいたかがわかりますし、中でも面白い曲をつなげてお贈りしたいと思います。
次に、ダニエル・パーセルですが、彼は、イギリス音楽を代表する作曲家ヘンリー・パーセルの弟です。ヘンリーは30代半ばで亡くなってしまうのですが、ダニエルはヘンリーの晩年に兄を助けて曲を作るようになり、めきめきと力をつけ、亡くなった兄の跡を継いで劇場の作曲家として大活躍しました。兄から受け継いだもの、自分のテイストの入ったもの、その両方が入っている作品をお届けします。兄の作風と似ているのはちょっと兄弟愛も感じられますね。
──会場では当時の雰囲気を灯りで演出するそうですね。
はい。バロック時代は電気のない時代ですので、劇場でもろうそくの灯りの中で演奏されていました。炎が揺れ動く様子まで再現されているLEDの灯りを使って、それを舞台上の色々な所に置いて当時の雰囲気も味わっていただきたいと思います。
──持ち込んでいただく白いチェンバロも素敵な楽器ですね。
 チェンバロの村上さんが所有している楽器ですが、17世紀頃に日本の柿右衛門などの陶磁器がヨーロッパの貴族に大流行しまして、楽器にも中国や日本の美術の影響が見られ、このチェンバロには美しいシノワズリ※の柄が大変繊細に描かれています。当時の貴族に流行っていた柄そのものを再現した楽器です。
チェンバロの村上さんが所有している楽器ですが、17世紀頃に日本の柿右衛門などの陶磁器がヨーロッパの貴族に大流行しまして、楽器にも中国や日本の美術の影響が見られ、このチェンバロには美しいシノワズリ※の柄が大変繊細に描かれています。当時の貴族に流行っていた柄そのものを再現した楽器です。

