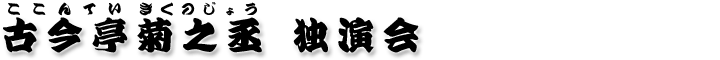滑らかな語りで笑いの渦に 江戸にいざなう菊之丞落語

本公演は終了しました
2012年11月17日(土) 14:00開演
| 【全席指定】 | 会員2,700円 一般3,000円 高校生以下1,000円 |
| 500円、対象:1歳~未就学児、定員10名、要予約(2週間前まで) *未就学児は入場できません。 |
|
| 【演 目】 | 開口一番 三遊亭しあわせ 落 語 春風亭朝也 落 語 古今亭菊之丞 仲入り 紙切り 林家正楽 落 語 古今亭菊之丞 お囃子 松尾あさ社中 |
粋でいなせな横丁の若様のような姿が凛々しい古今亭菊之丞。
洒脱でありながら、どっしりと座りの良い落語をお楽しみください。
星のホールで3回目の独演会となる古今亭菊之丞師匠にお話を伺いました。
──三鷹での独演会は今回で3回目となりますが、星のホールやお客様の印象はいかがですか?
 大変やりやすいのびのびやれるホールですね、お客様はツボツボで笑ってくださいますし、ちゃんと聞いてくださるので、非常に演者はやりやすいですよね。
大変やりやすいのびのびやれるホールですね、お客様はツボツボで笑ってくださいますし、ちゃんと聞いてくださるので、非常に演者はやりやすいですよね。
──師匠は東京の渋谷のご出身ですよね。
一応、渋谷とはなっていますけれども、子どもの頃に井の頭線沿線の浜田山に移って小学校の仕舞いまでおりまして、それから20年は母の実家のある千葉県の市川におりました。
──小さい頃はどんなお子様だったのですか?
変な子どもだったみたいですよ。私が小学生の頃は、まだテレビの演芸番組がたくさんありましてよく見ていましてね、そこで着物を着て座布団の上に座って喋っている落語家に非常に興味を持ちまして、中学に上がってからは友達の前で落語をやったりもしていましたから。そうしたら偶然、担任の先生が落語が大好きで、子どもの頃から寄席に行っていたような方で、「お前、上野にある鈴本演芸場行ってみろ、面白いから」と言われて行ってみると、「こんなに面白いものなんだ」と改めて思いましたね。
最初は、噺ではなく、落語家を見に行っていたんです、有名な落語家が一杯いらっしゃいましたからね。ただ、行っているうちに段々、これは落語家じゃなく“落語”を楽しむ場所なんだということに気が付きまして、無名な方でもとてもうまい方が沢山いらっしゃったんですね。噺に引き込まれて、落語っていうのはすごいものなんだ、と。それがわかっちゃう中学生って変でしょ(笑)。
──高校を卒業されてからすぐに弟子入りされたのですか?
一応大学は受けたのですが、大学側と私の意見に相違がありまして(笑)、「うちは結構です」と言われ、私も素直に「あ、わかりました」って(笑)。で、古今亭圓菊*に弟子入りしました。
──たくさんのお師匠さんの中から、どういう理由で圓菊師匠を?
古今亭ファミリーが好きだったんですよ。とっくにお亡くなりになっていますがトップは志ん生師匠、その息子さんで亡くなった志ん朝師匠がいて、先代の志ん馬師匠がいて、その下にうちの師匠がいて、色々な方を見に行っているうちに、うちの師匠はとても温かみのある落語をやる人なんだなと思って、それでもう「この人に決めた!」と。
──入門はどのようにされたのでしょうか?
 本来は、楽屋に訪ねて行って、あるいはご自宅を調べて訪ねて行って、何度もお願いをして、何度も断られて、それでもしがみついて、それでやっと、という感じで普通は入るんですけども。実は私は子どもの頃から、演芸評論家の大家で志ん生師匠の本を何冊も書いていらっしゃる小島貞二という方と知り合いだったもので、その先生にお願いしましたら、その場で師匠に電話してくださったんですよ、「もしもし小島です、お宅に行きたいって若いのがいるからお願いします。」って。これで入門が通っちゃいました。でも、これは後から師匠に怒られましたねぇ、「お前は汚ねぇ野郎だなぁ、俺が断れない人を介して入ってくるんだもん、ズルいよ!」って(笑)。「だからお前は、より一生懸命修業しなきゃいけないよ!」とも言われましたね。
本来は、楽屋に訪ねて行って、あるいはご自宅を調べて訪ねて行って、何度もお願いをして、何度も断られて、それでもしがみついて、それでやっと、という感じで普通は入るんですけども。実は私は子どもの頃から、演芸評論家の大家で志ん生師匠の本を何冊も書いていらっしゃる小島貞二という方と知り合いだったもので、その先生にお願いしましたら、その場で師匠に電話してくださったんですよ、「もしもし小島です、お宅に行きたいって若いのがいるからお願いします。」って。これで入門が通っちゃいました。でも、これは後から師匠に怒られましたねぇ、「お前は汚ねぇ野郎だなぁ、俺が断れない人を介して入ってくるんだもん、ズルいよ!」って(笑)。「だからお前は、より一生懸命修業しなきゃいけないよ!」とも言われましたね。
──修業時代は楽しいこともあれば辛いこともあったかと思いますが?
楽しいってことは、まずないですね、修業ですから。それこそ3年半、前座をやりましたけれど、休みがないんですよ、1日も。元日から大晦日まで、朝から必ず師匠の家に行って、トイレ掃除から玄関掃除、とにかく掃除していました。それが終わって寄席に行って、いろいろ洗い物したり着物を畳んだりと、そんな雑用の毎日でした。
──その中で忘れられない出来事はありますか?
忘れられないと言いますか、とにかく師匠は小言魔でした。昨日良かったことが今日ダメだったりするわけなんですよ。ある時楽屋で、師匠が帰る時に、パッと鞄を持って行っちゃったのですが、その時に私は脇で雑用をしていたもので、遅れて「師匠すみません、お鞄お持ちします。」と言ったら、「ばか野郎!弟子が師匠の鞄を持つのは当たり前だろう!」って怒られて。で翌日、同じしくじりをしちゃいけないと、へばりついていたんですよ。で、師匠が立ち上がった途端に鞄を持ったら、「じじぃじゃねぇんだよ俺は!!」って鞄をひったくられました(笑)。もう日によって違うんですよ、どっちに転んでも小言(笑)、そんな修業です。でもやはり、そういった理不尽をかいくぐった人じゃないと、多分、落語家としては生き残っていかれないんじゃないかと思います。
──そういう時代を経て、初めて高座に上がった時のことは覚えてらっしゃいますか?
もう忘れもしません、1991年10月10日、新宿の末広亭という寄席で「子ほめ」というネタで高座に上がったわけですよ。そうしたらね、私がこの世界に入るきっかけになった中学の担任が客席にいたんですよ(笑)。途端にわからなくなってネタが飛んじゃいましたね(笑)。何とかオチまではやりましたけれども、メロンメロンになって高座から降りてきたことを強烈に覚えています。あれからもう21年ですよ。
──2003年に真打になられて、色々な土地での思い出もあることかと思いますが、なかなか味わえない珍しい場所での高座とかありましたか?
二つ目になってから、船に乗るようになりましてね、いわゆる世界一周クルーズが復活し始めた頃で、その船内で毎日落語をというお仕事をいただきましましたね。着物を持って、北はアイスランドから南はオーストラリアまで色々な国に行って、船の上で『船徳』とかやりました。船が先に進まずに、ぐるぐるその場を回っちゃう噺なんですけれど、まぁいいや、って(笑)。船の旅は長いですから、同じショーばかり見ていると飽きてしまうその点、毎日違う噺をやれる落語家は重宝するみたいです(笑)。
──演目は予め決めてらっしゃるんですか?
寄席の場合は、先に出演した噺家から、何の噺が出るかわからないんですよ。出番の直前に今日出たネタの帳面を渡されるので、それを見てまだ今日出ていない噺をやる、それは全く同じ噺というだけではなくて、お酒の噺が出ていたら同じような酔っ払いのネタの噺は避けるとかもあります。ですから、昼からずっとやっている寄席の一日の最後を〆る、夜の部のトリというのは、腕がないと務まらないですね。
──普段から心掛けていらっしゃることはありますか?
落語に関しては、なるだけ江戸の風情は損なわないように、江戸の言葉で話したいと心掛けています。私も随分お客様方から指摘されまして…「ら」抜き言葉とかね。今のお客様は皆さん突っ込んできますから。でも、それって普段からやっていないとダメなんですよね、なるだけ普段もそういうことは気を付けておしゃべりはしているんですが。
──師匠の書かれた本の中に「語るんじゃなくて会話をしろ」とありましたが。
特に落語って芸は、AさんとBさんが喋りながらすすめていく芸で、これはまず前座の時にうちの師匠に言われたのですが、「絶対に、演じてはダメ。笑わせてやろう、よく聞かせてやろう、演じてやろう、と思っちゃダメ!」と。また、これは柳家小三治師匠に言われたことで、「落語家は落語の筋を知っている、ほとんどのお客様も大体筋は知っている。その代わり、噺の中に出てくる主人公たちは、この後の展開は知らないんだよ。毎回同じ落語をやっていても、絶対毎回違う反応になるはずだから、同じようにやっていちゃダメ」と。これって、うちの師匠が言っていることと同じなんですね。あんなに芸風の違う師匠方が、同じ目的に走っているんだと知った時に、落語ってすごいなって思っちゃいました。同じ落語でも落語家が違うと全然違った噺に聞こえちゃうっていうのが、本当に面白いんですよね。
──今日は素敵な浴衣姿ですが、普段も着物とか浴衣をお召しなのですか?
洋服も多いですけれど、半々ですね。これは落語協会の浴衣で、今日は銀座線でファンの方にお声かけていただきました。この姿だからわかるんですけれど、洋服だと気付かれないですね。あの志ん朝師匠ですら、普段はすれ違っても気付かれなかったです。落語家が帽子被って眼鏡かけているなんて思わないじゃないですか、普段も着物姿で歩いているように思いますよね。そうでもないんです、意外に洋服が多いんです。
──お忙しい毎日かと思うのですが、お時間のある時はどんなことをしてお過ごしですか?
お客様からはあまり飲めるとは思われていなくて、「下戸(げこ)なんでしょ?」なんてよく言われますが、結構あちこちで飲んでいます。カラオケがある店が好きですね(笑)。
──歌っていらっしゃる映像をインターネットで拝見しました。コールがかかっていましたが、十八番の曲なのですか?
お、見ましたか、例のあの曲を(笑)。「加賀の女」、これは古今亭の我々のテーマソングになっているんです。飲み屋でやるんですけれどね、サビで両手を上に大きく突き出して「か・な・ざ・わ・は〜」って振りを、合わせて皆でやるんですよ。
──さて、11月17日に星のホールに登場となりますが、秋ということでどんな独演会を考えてらっしゃいますか?
 前回は夏だったので、『唐茄子屋政談』ですとか『鰻の幇間』などの、夏の噺をやりましたけれども、今回は秋に、と言いますか、もう暮れですから冬の噺になるわけなんですよ。この時期にしか出来ない落語ってのもありますから、一つ二つ考えているネタはあります。ここでどのネタかをお話するのは控えますが、秋冬の噺を楽しんでいただこうと思っております。
前回は夏だったので、『唐茄子屋政談』ですとか『鰻の幇間』などの、夏の噺をやりましたけれども、今回は秋に、と言いますか、もう暮れですから冬の噺になるわけなんですよ。この時期にしか出来ない落語ってのもありますから、一つ二つ考えているネタはあります。ここでどのネタかをお話するのは控えますが、秋冬の噺を楽しんでいただこうと思っております。
──最後にお客様にメッセージをお願いいたします。
本当に三鷹の会は我々が楽しみにしている会でございます。寄席と違いまして時間をたっぷり取っていただいているものですから、時間を気にせずお客様に楽しんでいただける会だと思います。11月の17日でございます、ぜひお運びをいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
──お客様に着物で来ていいただくのはどうですか?
来ていただけると本当に我々も張り合いが出るわけですけども、ただ、目が悪いものですから、あまり見えないんですね(笑)。ので、前の方の席で見ていただいて(笑)、客席も華やかになりますしね。
*本インタビュー収録後の10月13日に古今亭圓菊師匠がお亡くなりになりました。謹んでご冥福をお祈り申しあげます。