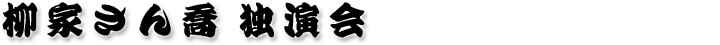沁みいる落語で 今年を締める 暮れの三鷹は 柳家さん喬

[昼の部完売]
本公演は終了しました
2011年12月17日(土) 昼の部14:00 夜の部18:00開演
| 【全席指定】 | 会員3,150円 一般3,500円 高校生以下1,000円 |
| 500円、対象:1歳~未就学児、定員10名、要予約(2週間前まで) *未就学児は入場できません。 |
|
| 【番 組】 | 開口一番 落語 昼の部 柳家喬之進 夜の部 柳家さん弥 落語 柳家さん喬 仲入り 紙切り 林家二楽 落語 柳家さん喬 お囃子 金山はる社中 |
通を唸らせつつも、滅多に落語を聴かないという人をも一瞬で魅了してしまう、柔らかくも滑らかな語り口。ぜひ、一度味わっていただきたい本格派、柳家さん喬師匠の落語を、ご堪能ください。
Interview 柳家さん喬
昔の生活は、情にからんだもっとあたたかな笑いに包まれていた、と思うんですよね。
毎回その滑らかな語り口でお客様を魅了される、柳家さん喬師匠にお話を伺いました。
──星のホールでは今回が6回目の独演会となりますが、三鷹での落語会はいかがですか?
 いつも満席のお客様にお越しいただいて本当にありがたいことです。落語は300席くらいまでの会場が丁度良いと思いますが、その点でもこちらは最適ですね。(星のホールは250席)また三鷹のお客様は雰囲気がやわらかいと感じます。「ここではこんな聴き方や楽しみ方をするんだよ。」という常連のお客様の雰囲気が、遠方からのお客様や落語会に来るのは初めてというお客様にも、とても聴きやすくておいでなのかなと感じることがあります。
いつも満席のお客様にお越しいただいて本当にありがたいことです。落語は300席くらいまでの会場が丁度良いと思いますが、その点でもこちらは最適ですね。(星のホールは250席)また三鷹のお客様は雰囲気がやわらかいと感じます。「ここではこんな聴き方や楽しみ方をするんだよ。」という常連のお客様の雰囲気が、遠方からのお客様や落語会に来るのは初めてというお客様にも、とても聴きやすくておいでなのかなと感じることがあります。
──寄席のお客様は、噺家の方が舞台に一歩出てきたときから注目していますね。
そうですね。落語家が登場するときに演奏される「
──高座 で緊張されることはありますか?
噺家になりたての頃は吐きそうになるほど緊張したものですが、今は楽屋で出演する土壇場までしゃべっていますね(笑)。そのほうがリラックスして話せるように思います。内側の緊張だけはそのままに、お客様にはその緊張を悟られてしまわないようにすることが大事ですね。
──ご出身は墨田区の本所でいらっしゃいますね。
本所というところは橋を渡ると浅草という所ですので、昔から色々な娯楽が身近にあふれていました。その頃の浅草は、当時大変人気があった女剣戟などのいわゆる軽演劇をはじめ、六区と呼ばれたかつての興行街にはお芝居あり、歌あり、映画ありと大変な賑わいでした。そんな場所をお爺さんや父に手を引かれて歩いているうちに、自然と芸事というものに親しんでいたんだと思います。
──では、子どもの頃から落語家になろうと思っていらっしゃったのでしょうか?
 いえ、そうは思っていませんでした。当時は学校の先生になるのが夢でしたから。ところが高校生のときに学生運動が起こり、大学進学を諦めざるを得なくなりました。そして・・・気がついたら、三鷹で落語をしていました(笑)というような感じですね。
いえ、そうは思っていませんでした。当時は学校の先生になるのが夢でしたから。ところが高校生のときに学生運動が起こり、大学進学を諦めざるを得なくなりました。そして・・・気がついたら、三鷹で落語をしていました(笑)というような感じですね。
昔はテレビよりもラジオが主な娯楽で、番組も笑いを中心としたものが多かったんですね。また私は色々な芸事が身近にあるという環境で育っていくうちに、面白いとか楽しいという事がどういう事なのかが、自然と身についていったんだと思います。その頃の笑いって人情にあふれた、あたたかな笑いだったと思うんです。残念ながら今テレビを見ていると時折「これが笑い?」と思うことがあります。人をクサしたり悪口を言ったりすることを笑いにつなげる、「日本の笑いってこんなに幅のせまいものだったのか」って思うことがあります。昔の子どもたちは、情にからんだもっとあたたかな笑いにいつも包まれていた、と思うんですよね。
──落語家になる際の「弟子入り」はどのようにするのですか?
恋人を選ぶようなもんですかね(笑)。毎日戸口に立って自分の帰りを待っていて「おかえりなさい、好きです。」って何度も言われていると「そんなに好きなら自分も好きになってやろうか」と思うこともあるでしょ(笑)。弟子入りにもそういうところがあって、次第にこちらも情が移ってしまってね・・・。もちろん弟子をとるということはその人の人生をお預かりする訳ですから、それだけの責任もあります。弟子になれば実の子どもと同じとはいいませんが、それに近い感情で接しますから、折りにふれてかばってやったり、逆に突き離してみたりもするのが師弟です。弟子にするにあたって何回かは断ったり、時には少し世間話などをしたりする中で、その人となりや、本当にやる気があるのかといったことを確かめるんです。
──ご自身が弟子入りされた5代目柳家小さん師匠は、どのような師匠でいらっしゃいましたか?
世の中で一番尊敬する人は?と聞かれたら、素直に小さん師匠ですと答えたくなる素晴らしい師匠でした。実際にその懐へ飛び込んでいかないと、その本当の素晴らしさは解りませんから。ただ落語が上手いとか人徳があるという言葉で納得するよりも、その懐へ入って、そのぬくもりを感じたときに「ああ、やっぱりすごいな・・・」と感じましたね。
──現在では三鷹でもお馴染みの柳家喬太郎さんを筆頭に、10人以上ものお弟子さんをお持ちですが、芸をどのように伝えていこうと思っていらっしゃいますか。
落語の場合は芸の伝承っていうのはなくて、あくまでも芸は個人のもので一代限りのものなんです。それはなぜかというと落語の芸は一人の噺家とお客様それぞれ一対一のものであって、お客さまが100人でも1000人いらしても同じく一対一なんです。それぞれの持ち味を生かして後世へどう伝えていくかという事ですね。丸々伝えるという事はしないし実際にそれは無理なんです。対して歌舞伎などではそれがきっちりとされていますので、美しさや形を総合的な芸術として残してゆくことができますが、落語というものはそういうものじゃありません。「ここでは間をこれだけとりなさい。」とか「ここで隠居さんは1秒待って次のセリフを言いなさい。」などということはないんです、では弟子へ伝えてゆくものは何かというと、その噺の雰囲気とか時代といったことでしょうか。
師匠小さんが良く使っていた「
──同じ噺でも毎回違うということに落語を聴く楽しみがありますね。
そうなんです。同じ噺でも語る人によって違う。笑う場所も違う。じゃあ言葉は変わっているかというと変わっていない。不思議な芸能だなぁと思いますよねぇ。
──落語の他にお好きな事はありますか?
 最近は休みが無いので、ぜひとも昼寝をしてみたいですね(笑)。若い頃は休みといえば、落語に活かそうと映画や芝居を観たりということもしていましたが、最近はもうごろっとしていたいですね(笑)なかなかそれもできませんが。まあ、しいていうと、これを趣味といっていいのかわかりませんが、ぼやーっとして行き交う人たちを見ているのが好きですね。特にバスの待合所なんて面白いんですよ。スーパーの袋を持った一人のお爺ちゃんがいるとします。袋の中身はそばつゆの瓶。この方はこれから家に帰って、お嫁さんにお願いして蕎麦を作ってもらうのかしら?それとも自分で作って一人で食べるのかしら?などと想像していくのがとても楽しくて。興味本位で観るのではなくて、人それぞれが持つバックボーンといった事にとても興味があります。
最近は休みが無いので、ぜひとも昼寝をしてみたいですね(笑)。若い頃は休みといえば、落語に活かそうと映画や芝居を観たりということもしていましたが、最近はもうごろっとしていたいですね(笑)なかなかそれもできませんが。まあ、しいていうと、これを趣味といっていいのかわかりませんが、ぼやーっとして行き交う人たちを見ているのが好きですね。特にバスの待合所なんて面白いんですよ。スーパーの袋を持った一人のお爺ちゃんがいるとします。袋の中身はそばつゆの瓶。この方はこれから家に帰って、お嫁さんにお願いして蕎麦を作ってもらうのかしら?それとも自分で作って一人で食べるのかしら?などと想像していくのがとても楽しくて。興味本位で観るのではなくて、人それぞれが持つバックボーンといった事にとても興味があります。
師匠小さんの「うどん屋」という噺を聞いた時にね、ある男が幼い頃から娘のように可愛がっていた近所の娘が嫁いだ日の噺で、酔っ払った男が本当に娘が可愛かったということをひとしきりしゃべった後にうどん屋に一言、「めでてえなぁ・・・うどん屋。」とつぶやくんです。その一言で舞台上にいないはずの登場人物達の顔がふわぁっと姿を現し、見えてくるんですよ。見えていないものが見える、すごいことだなぁと思うんですよ。そんな事に憧れて勝手に想像して噺を作って楽しんでいる。だから、行き交う人を見るのが好きなのは、師匠の影響ですね(笑)。
──演目はあらかじめ決められているんですか?それとも当日高座に上がられてから決めるのですか?
上がって決めることもありますね。でも高座はある種の戦いですから、一応作戦は練る訳ですよ。楽屋で今日はどんなお客さんが来ているのかとか、自分の前に出演している人は何を
──12月17日のさん喬師匠の独演会が、今年の星のホールでの最後の落語会となります。
今回はお客様には師走のお忙しい中、お越しいただく訳ですから、一年の締めくくりとして楽しく笑っていただきたいですね。また、私にとっても今年最後の独演会ということで気を引き締めて頑張りたいと思っています。