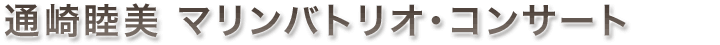カラフルなマレットからはじけ出す軽やかな音色。音符が今、踊り出す!

©平野 愛
[チケット発売日] 会員12/8(火) 一般12/11(金)
2010年 3月22日(月・祝) 15:00開演
| 【全席指定】 | 会員2,500円 一般3,000円 シニア(60歳以上)2,500円 中高生1,500円 小学生1,000円 |
| 500円、対象:1歳~未就学児、定員10名、要予約(2週間前まで) *未就学児は入場できません。 |
|
| 【出 演】 | 通崎睦美(つうざきむつみ)、今田香織、後藤ゆり子 |
| 【曲 目】 | スペイン(作曲:E.シャブリエ / 編曲:土肥寿美子) グラスホッパーズ(作曲:坂本龍一 / 編曲:通崎睦美) シネマ(作曲:E.サティ / 編曲:野田雅巳) ほか |
| 【サイト情報】 | 通崎睦美 ウェブサイト http://tsuuzaki.j-spirit.com/ |
京都の風呂敷職人の家に生まれ5歳よりマリンバを始めた通崎睦美は、京都市立芸術大学を卒業後、91年のデビューコンサートを皮切りに「人とは違った、自分自身にしか表現できないもの」を探し続け、常に新しい音楽に取り組むマリンバ奏者です。これまでにピアノやオーケストラはもちろん、ヴァイオリン、アコーディオンや日本の伝統楽器である箏や三絃などとの奏者とコラボレーションし、多種多様な演奏活動を行ってきました。
木琴の巨匠、故・平岡養一氏が1944年に初演を行った『木琴協奏曲』(作曲:紙恭輔)を2005年に再演するという試みにおいてソリストに抜擢され、その演奏が高い評価を得たことにより平岡氏の遺族から彼が愛用していた1935年製の木琴をはじめ、500曲以上にものぼる楽譜とマレットを譲り受けました。以後、彼の軌跡をたどりながら木琴の新たな可能性を探る活動も行っています。今回は魅力あふれる選曲で、3人のマリンビストによるコンサートをお贈りします。
◎関連プログラム
通崎睦美と作ろう! 春の手作り木琴ワークショップ


ワークショップイメージ木琴についてのお話しの後、実際にのこぎりで木を切って、世界でたった一つの“オリジナル木琴”を作ります。音の高さや音階はみんなそれぞれ。色を塗ってデコレーションも楽しめます。
Aグループ 3月20日(土) 10:30〜16:30
Bグループ 3月21日(日) 10:30〜16:30
*A・Bは同じ内容です。
| 【会 場】 | 三鷹市芸術文化センター B1Fアートスタジオ |
| 【講 師】 | 通崎睦美、岩野勝人(彫刻家) ほか |
| 【対 象】 | 小学4年生以上 定員:各グループ20名 |
| 【申込開始日】 | 会員12/8(火) 一般12/11(金) |
| 【参加費】 | 3,000円(材料費2,000円込) *作業補助のためにお子様とペアで参加される大人の方 1,000円 |
| 【持ち物】 | *のこぎりや彫刻刀を使用します。*作業しやすい服装でお越しください。 |
Interview 通崎睦美インタビュー
古き良きものを改めて見直してみると、色々な可能性がみえてくるのではないかと思って…。
物の価値を見い出す確かな目と並々ならぬ好奇心。
マリンバ奏者、プロデューサー、アンティーク着物コレクター、エッセイスト…。
様々な活動で「自分自身にしか表現できないもの」を探し続ける通崎睦美さんにお話しを伺いました。
──マリンバは5歳のとき習い事として始められたそうですね。
 そうなんです。京都の風呂敷職人の家に生まれ、歌舞伎などには連れて行ってもらっていましたが、オーケストラの演奏会は聴いたことがなくて、クラシック音楽には無縁でした。それが、5歳の時姉が通っていた音楽教室で見た時に「これがいい!」と言って始める事になったんです。座って演奏する楽器より、立って、動き回って演奏している姿を観てカッコイイ!と…。その後、中学の管弦楽部でベートーヴェンを聴いて衝撃を受け「これだ!」と思い、クラシックの道へ進むことを決意しました。高校は音楽専門の学校へ進み、大学ではオーケストラのパーカッションなど打楽器全般を学びました。でも、マリンバは子どもの頃からやっていて一番好きですし、なんといってもメロディーを弾けるのが楽しくて魅力ですね。
そうなんです。京都の風呂敷職人の家に生まれ、歌舞伎などには連れて行ってもらっていましたが、オーケストラの演奏会は聴いたことがなくて、クラシック音楽には無縁でした。それが、5歳の時姉が通っていた音楽教室で見た時に「これがいい!」と言って始める事になったんです。座って演奏する楽器より、立って、動き回って演奏している姿を観てカッコイイ!と…。その後、中学の管弦楽部でベートーヴェンを聴いて衝撃を受け「これだ!」と思い、クラシックの道へ進むことを決意しました。高校は音楽専門の学校へ進み、大学ではオーケストラのパーカッションなど打楽器全般を学びました。でも、マリンバは子どもの頃からやっていて一番好きですし、なんといってもメロディーを弾けるのが楽しくて魅力ですね。
──91年にマリンバ奏者としてデビュー後は、ご自身で色々なコンサートをプロデュースされていますね。
20年くらい前は、ほとんどマリンバの楽譜は売っていなくて、ヴァイオリン等の曲をそのままやるか、現代曲のどちらかというのが主流だったんですね。そんな状況でしたから、自分で弾きたいと思う曲を編曲するか作ってもらうしかなくて…。当時、今ほど一般的ではなかったピアソラの作品や『子どものためのアジアのわらべうたと伝統音楽』(ユネスコ・アジア文化センター)という膨大な資料の中からアジアの国々の曲を探してきたり、その他にもマリンバの音色に良く合う響きの曲を選んでは編曲してもらいました。また編成もマリンバとピアノだけじゃなくて、箏や三絃、ダンス、タンゴバンドなど色々な編成で演奏してきました。
──木琴の巨匠、平岡養一氏のご遺族から氏の木琴や楽譜を譲り受けたことで、木琴の演奏や研究もされていますね。
 マリンバと木琴(シロフォン)って、形は似ているけど全く別の楽器なんです。諸説ありますが主なルーツを言えば、木琴はヨーロッパ、マリンバはアフリカ。当然、似合う曲も変ってくるんですが、現代のコンサートで主に用いられるのは、より響きが豊かでゴージャスなマリンバなんです。木琴のようにあまり使われなくなってしまったけれど、古き良き物も改めて見直してみると、色々な可能性がみえてくるのではないかと思って…。物には意外な使いみちがあると思うんですよね。
マリンバと木琴(シロフォン)って、形は似ているけど全く別の楽器なんです。諸説ありますが主なルーツを言えば、木琴はヨーロッパ、マリンバはアフリカ。当然、似合う曲も変ってくるんですが、現代のコンサートで主に用いられるのは、より響きが豊かでゴージャスなマリンバなんです。木琴のようにあまり使われなくなってしまったけれど、古き良き物も改めて見直してみると、色々な可能性がみえてくるのではないかと思って…。物には意外な使いみちがあると思うんですよね。
──確かに木琴のコンサートってあまり無いですね。音楽活動の他には、アンティーク着物やライフスタイルについての本を執筆されたり、ゆかたのプロデュースもされています。
大正生まれの伯母の着物を受け継いだときに、昔の着物がとても「生きている」感じがして魅力を感じました。現代では普段は洋服を着るようになって、着物は儀式の時に着る特別なものになってしまったけれど、当時はみんな普段着として着物を着ていて、例えば今でいうところのセレブが誂えたような高価なものから、ユニクロで買えるようなものまで色々あったんです。「 古いもの」が好きですね。今、自分がここでその価値を見出して次の世代に受けついでいかないと、無くなってしまいそうなもの… 木琴も同じです。今、放っておくとそのうち完全に忘れ去られてしまうと思って…。
──普段の生活の中にある楽しみを見出す、発見の名人ですね。
 発見好きです(笑)。人がまだやっていない新しいことをするのが楽しいですね。人が発見してくれるのも嬉しい。みんな何か発見すると嬉しくなるでしょ? 普通のことでも見方を変えると「へぇー。」ってこともある。コンサートでもお客さんに何か新しいコトを発見してもらいたいんです。
発見好きです(笑)。人がまだやっていない新しいことをするのが楽しいですね。人が発見してくれるのも嬉しい。みんな何か発見すると嬉しくなるでしょ? 普通のことでも見方を変えると「へぇー。」ってこともある。コンサートでもお客さんに何か新しいコトを発見してもらいたいんです。
──木琴作りのワークショップについて教えてください。
のこぎりで木を切って自分で作りたい音階を作るんですが、ほんの数ミリ削っただけで、音が変わる。この作業に皆さん結構ハマります。必ずしもドレミファソラシドでなくていい。以前、「魔女の音がする木琴を作る」といって不思議な短調の音階を作った小学生がいました。他にも「楽器を作るのが趣味です」とおっしゃる60代のおじさまや、カップルでの参加など幅広い年代の方々が参加しています。お孫さんのつきそいで来られたおばあちゃんが作業に夢中になってしまうこともよくあります。(笑)
──家族で参加して、みんなでアンサンブル! なんて楽しそうですね。風のホールでのコンサートはいかがですか?
ここでは録音をしたこともありますが、響きも良くてマリンバに合っているし、弾いていてすっごく気持ちがいいです。プログラムは、大人が聴いても、子どもが聴いてもそれぞれに楽しく新しい「発見」があるようなものにしたいと思っています。