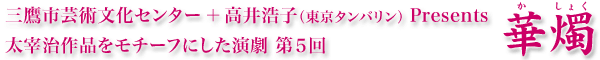太宰治へのオマージュとしての演劇公演の第5回。
太宰の作品からヒントを得て、若手作家が独自の世界を描きます。現代版太宰にご期待ください!

2006年「ワルツ」撮影:青木司

高井浩子(東京タンバリン)
[チケット発売日] 会員5/22(木) 一般5/23/(金)
2008年6月27日(金)〜7月6日(日) 全12回公演
| 【全席指定】 | 前売:会員=2,700円 一般=3,000円 当日:会員=3,150円 一般=3,500円 高校生以下=1,000円(前売、当日とも) |
| 500円、対象:1歳〜未就学児、定員10名、要予約(2週間前まで) *未就学児は入場できません。 |
|
| 【作・演出】 | 高井浩子 |
| 【出 演】 | 今井朋彦(文学座)、井上幸太郎、佐藤 誠(青年団)、瓜生和成、森啓一郎、 坂田恭子、ミギタ明日香、遠藤弘章、大湯純一、大田景子 ほか |
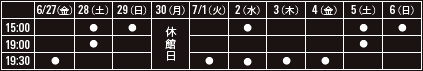
『没後60年、いまだに根強い人気を持つ太宰治は、その作品の中に日本人の精神に必ず抱合されている「弱さ」を否定的でないものとして、表現しているところに魅力があります。「 弱さ」という普遍性を新たな視点で検証し、太宰治をあらためて再確認していきます。 太宰治の退廃的といわれる作品に内包される人間の「不条理」や「深部に存在する流動する世界」を具象と抽象を織り交ぜながら表現していきます。』 高井浩子
東京タンバリン
高井浩子の劇作を本人演出のもと上演する目的で1995年設立。「何が本当で何が嘘なのか」「意識と無意識の中で揺れ動く人間の闇」を描き出す表現にこだわりを見せます。 2006年9月の三鷹公演では舞台と客席を真二つにし、背中合わせで同時進行の2作品を上演し(「ワルツ〜隣の男〜」「立待月〜隣の女〜」)話題になりました。
Interview 『華燭』 高井浩子 & 今井朋彦
太宰治作品の持ち味と、人間の内面の葛藤を浮き彫りにする東京タンバリンの芝居とを、
融合させた世界を展開したい…
三鷹は太宰治が昭和14年から約9年間、亡くなるまでを過ごした街であることにちなみ、三鷹市芸術文化センターでは、
2004年から太宰治作品をモチーフとした演劇を上演しています。今回は、今年この舞台を手がける「東京タンバリン」主宰の
高井浩子さんと、主役の一人を務める文学座の俳優、今井朋彦さんにお話を伺いました。
最初にこの企画の依頼があったときには、どのような感想をお持ちでしたか?
高井:太宰治の作品は大好きなのでうれしかったですが、三鷹でやるとなるとファンも多いだろうと思い、プレッシャーはありましたね。
今井さんに出演していただこうとは、すぐに思いついたのですか?
高井:はい!この人しかいないと思いました(笑)。
今井さんは「東京タンバリン」の舞台をよくご覧になっているそうですね。出演依頼があったときの感想はいかがでしたか?
今井:高井さんも僕の舞台を何回か観てくださっていたのですが、僕のほうもこれまでに何回も通って観ていた劇団の方から、期せずしてお話をいただいたので、うれしさもまた格別でした。
太宰治作品をモチーフにした演劇という点はいかがでしょうか?
今井:僕は実は申し訳ないのですが、小学校の時の子ども会でやった「走れメロス」の“門番2”という役でくらいしか、これまで太宰作品との接点がなく(笑)…これを機会に読んでみたいと思います。
高井さんは、今回読み返されてみていかがでしたか?
高井:そうですね。中学、高校の頃は「この人はなんて女の人の気持ちがよくわかるんだろう」と思っていたんですが、今は、「人間の中のマイナス(負)の部分を、皆に普遍的にわからせるように示しているところがすごいな」と思います。
すでにもう稽古も始まっているとのことですがどんな舞台になりそうですか?
高井:いつもは現代口語演劇なんですが、今回は時代を昭和の初期に設定し、太宰治の中期から後期の作品*をモチーフにした四人の文士たちのお話になっています。
今井さんの役どころはどのような役ですか?
高井:その四人の中で、結構売れている作家の役です(笑)。
売れてもそうでなくても、自らの置かれた状況の中で必死にあがいている四人のお話になっています。
今井さんは稽古に入ってみてどんな感想をお持ちですか?
今井:「東京タンバリン」の劇団の中には、何年も何作品も一緒にやってきた人達のあうんの呼吸のようなものがあり、そういう雰囲気が魅力的だと思いますし、うらやましいとも思うところです。
今井さんはNHK大河ドラマ『新撰組!』や、テレビCMでのコミカルなお殿様役などにも出演し、幅広く活動されていますが、その中で舞台の持つ魅力とはどのようなものでしょうか?
今井:舞台の場合は、最低でも1ヶ月位の長い時間をかけて、他の俳優さんやスタッフの方達と交流していくわけで、その中で生まれてくる空気感、関係性が芝居の中で生かされた時に、日常の中では味わえない、何ものにも変えがたい魅力を感じますね。
高井さんにとって芝居を創ることの醍醐味はどんなことですか?
高井:そうですね。私も稽古場で新しいものが生まれるおもしろさと言うのを感じます。 自分で予測できないことが生まれてくる面白さ、それをたくさん創ってお客様に観てもらいたいと思います。
2年前に「Next Selection」という企画で公演していただいた時には、ホールの真ん中に壁があり、左右で2つの芝居が同時進行している、という斬新な使い方をされました。今回の舞台はまたちょっと変わった形式ですよね?
高井:ええ。今回は舞台を真ん中に配して、その両側にお客様に座って舞台を見ていただく形式となっています。
最後にお二人からお客様へメッセージをお願いします。
高井:太宰治の作品の持ち味を生かした、けれども「東京タンバリン」なりの面白さも生かした舞台を創りますので、ぜひ観にいらしてください。
今井:僕が持っている芝居の質、東京タンバリンの質、高井さんの筆の質とがうまく融合したものになればいいなと思っています。 よろしくお願いします。
*「 花燭」「家庭の幸福」「ダスゲマイネ」「おさん」「人間失格」など
(平成20年5月20日インタビュー)